ここ最近、農業を始める方がほんと増えていますね。
少し前ですが、国が以下の統計を公表していますのでご一読ください。
この調査結果を拝見して正直驚いたのは、”雇用就農は未経験者が8割以上を占めている”というのが驚きですが、それだけ農業に関心があるということの裏返しでもあるということです。
この記事では、
- 農業初心者が独立できるまでの期間
- 2つの就農パターンで違いを検証
についてご紹介していきます。
今回、就農というワードに目を向けてみると、個人で農場を開く「独立就農」と、農業法人の従業員として働く「雇用就農」という代表的な二つの就農パターンの違いを検証してみました。
農業初心者が独立できるまでの期間
まずは、将来「独立就農」を目指す場合いにはどれぐらいの期間が必要なのか探って行きたいと思います。
独立就農までの期間
一言で独立就農といっても、いきなり独立できるわけではありませんが、そのためには農業技術を学んだり農業知識を学んだりと一定の経験を積むことが必要になってきます。
独立就農までの近道として、まず研修制度を利用することがポイントです。
以下、研修を受けて活躍する新規就農者が活躍している事例です。
| 研修期間 | 研修内容 | 取得資格および免許 |
| 1年間研修(H27) | 座学、栽培実習、農業機械操作等、農業全般 | 劇物毒物取扱責任者、大型特殊免許を取得。 |
| 1年間研修(H27) | 座学、栽培実習、農業機械操作等、農業全般 | フォークリフト、ラジコンヘリコプター免許を取得。 |
| 1年間研修(H27) | 農業全般の座学、農家実習、農業機械操作等 | 大型特殊免許取得 |
| 2年間研修(H23~24) | お茶の生産・加工実習等の研修 | 大型特殊(農耕用)免許、 フォークリフト免許等を取得 |
| 研修期間(H24~25) | 農業全般の座学、栽培実習、農家実 習等の研修 | 農業技術検定2級、大型特殊免 許を取得 |
これらは農水省の公式サイトで活躍している事例になりまますが、独立就農を目指すひとにとってほぼ共通している特徴がありました。
- 研修期間:1年~2年
- 取得資格および免許:大型特殊
こらから就農を目指しているみなさんも、この二つを抑えて置くとよいですね。
こちらの事例以外でも、研修期間は1~2年のものが多いということがわかりました。
研修先はどこで見つける?
次世代の農業経営者を目指す人のために農業大学校という養成機関があります。
全国42道府県に設置されています。
授業料は養成課程で年額12万円程度が一般的ですが、そのほかに教材費や実習費、入寮する場合には寮費などの経費がかかることがあるので、事前によく確認しましょう。
就農希望者のほかにも、経営発展のためのスキルアップを目的とした授業や、農業技術や経営に関する研修も行われています。
| 対象 | 研修期間 | |
| 養成課程 | 高校卒業程度の人を対象 | 2年 |
| 研究課程 | 養成課程を卒業した人や短大卒業者 | 2年 |
| 研修課程 | 技術・知識の向上を目指す農業者の方 | 1日から数週間程度 |
各道府県の農業大学校一覧(農林水産省公式サイト)
2つの就農パターンの違いを検証

独立就農
実家が農家では無く、新たに農業経営を開始する場合のこと。
農業で生計を立てていくためには、しっかりとした栽培の基礎知識、害虫や農薬、農業機械等の知識や操作も含まれます。
また、経営者に必要な経営計画書の作成方法や簿記の知識が必要です。
独立就農はこんな人に向いている
- 自分の裁量で栽培・管理の年間計画を決めることができる人。
- 自分の確固たる方針や実現したい企画がある人。
就農初期投資は必要ですが、多額の準備費用は必要ないにしても就農初期の投資は必要で、20~30代の若い世代がいきなり独立就農に踏み出すには多少のハードルがありますが、将来的に独立したい人を支援する法人もあり、生活を安定させてから独立就農したい若い人には向いています。
雇用就農
雇用就農とは、農業法人の社員として雇用されるパターンで、働きながら栽培技術などのスキルを身に着ける就農方法です。
雇用先にもよりますが、平均的に年収で150万円~180万円になります。
一般企業に就職するのとは違いけっして多い賃金とは言えませんが、ここで少しづつでも就農に向けて貯金することが大事です。
また、国では二つの支援策を打ち出していますので受けられる主な支援策についてそれぞれ見てみます。
- 農業次世代投資資金 準備型
- 農の雇用
の支援策があります。
1.「農業時世代投資資金準備型」(旧青年就農給付金)
具体的な内容としては、個人事業者や農業法人等が研修生に対して行う実践研修を支援するもので、個人事業者・法人とも年間最大120万円を受給できます。
2.「農の雇用制度」
地域の担い手となる法人経営体を増やしていくため、農業法人又は経営の移譲を希望する個人経営者が就農希望者を一定期間雇用し、新たな農業法人を設立するために実施する、農業技術・経営ノウハウを習得させるための研修に対して支援します。
農の雇用事業には3タイプあり、それぞれ助成額や期間が異なりますが一番申請の多い次のタイプの支援だけ取り上げてみました。
農業法人等が就農希望者を新たに雇用し、就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための、実践的研修や外部専門家による研修等に対して支援。
- 助成金:年間120万円 ※ 研修生が障害者、生活困窮者、出所者等(以下「多様な人材」という。)の場合は年間30万円加算
- 支援期間:最大2年間
農家(農業法人)での研修制度
この研修制度では、会社で働きながら学ぶインターシップや農業体験とは大きく違い、その土地での就農を希望する人を対象に、現在進行系の義先進的技術や最新農業機械などを学びます。
自治体によって、テーマ別の複数の研修を用意しているのが特徴です。
また、研修修了後は、「雇用就農にするか」「新規就農をするか」を選ぶことになります。
研修期間は、自治体にもよりますが1年間〜2年間の研修が多いです。
3ヶ月や6ヶ月と短期のものもありますが、栽培技術や農業経営の知識を学ぶためには長期の方がフィードバックが大きいです。
また、自治体によっては就農準備のためのサポートがついている研修があります。
サポートの内容はさまざまですが、農地や農業機械、住宅などの準備を支援するという自治体もありますので、農林水産省の公式サイトをチェックしてみてください。
まとめ
この記事では、
- 農業初心者が独立できるまでの期間
- 2つの就農パターンで違いを検証
についてご紹介してきました
就農して活躍しているみなさんの状況を調べてみると1年〜2年の研修期間を経て、資格を取得して就農するという流れが顕著に見えました。
最後までお付き合いありがとうございます。



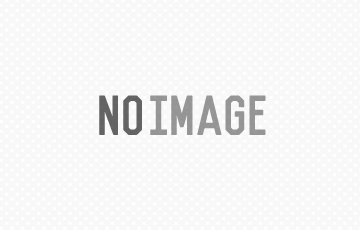






コメントを残す